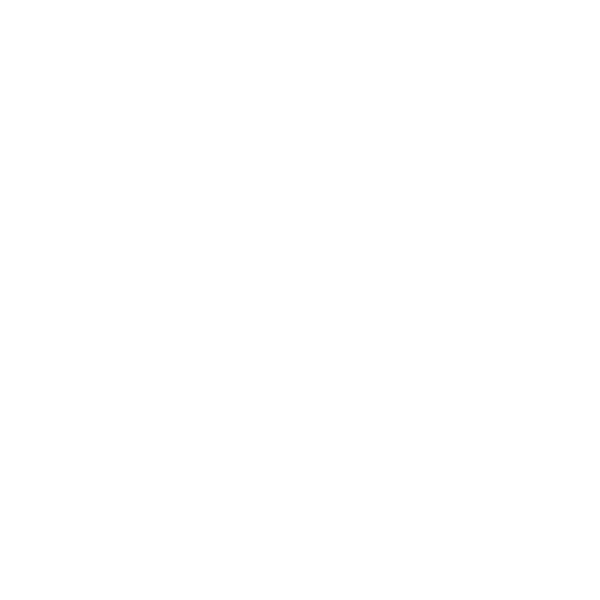101: Oracle Cloud で Oracle Database を使おう(BaseDB)
Oracle Base Database Service(BaseDB)は、Oracle Cloud Infrastructure 上で稼働する Oracle Database の PaaS サービスです。
オンプレミスと同じ Oracle Database ソフトウェアをクラウド上で利用でき、従来通りすべてのデータベースサーバーの管理権限(OS の root 権限を含む)や、データベース管理者権限を保持できます。
この章では、既存の仮想クラウド・ネットワーク(VCN)に新たなデータベースサービスを作成する手順を紹介します。
前提条件 :
- Oracle Cloud Infrastructure チュートリアル を参考に、仮想クラウド・ネットワーク(VCN)の作成が完了していること
- BaseDB の作成にはサービス・ゲートウェイが VCN に作成されている必要があります。
注意:
チュートリアル内の画面ショットは、Oracle Cloud Infrastructure の現在のコンソール画面と異なる場合があります。
**所要時間 :** 約30分
-
ナビゲーション・メニューから Oracle Database → Oracle Base Database Service を選択します。

-
DB システムの一覧ページで有効な管理権限を持つコンパートメントとリージョンを選択し、DB システムの作成 ボタンをクリックします。BaseDB の作成画面に遷移します。

-
表示された DB システムの作成 ウィンドウに、以下の項目を入力します。
※ がついている入力項目は課金に関係する項目です。
がついている入力項目は課金に関係する項目です。-
DB システム名 - 任意の名前を指定します。DB システムの名称として表示され、プロビジョニング後の変更はできません。
-
コンパートメント - BaseDB を作成するコンパートメントを指定します。(集合ハンズオン環境の場合は講師の指示に従ってください)
-
可用性ドメイン - BaseDB を作成する可用性ドメインを指定します。選択できる可用性ドメインはリージョンにより異なります。(集合ハンズオン環境の場合は講師の指示に従ってください)
-
Oracle Database ソフトウェア・エディション

下記エディションより 1 つ選択します。利用できる機能はエディションごとに異なります。プロビジョニング後の変更はできません。- Standard Edition - 標準的なエディションです。
- Enterprise Edition - 拡張機能を含むエディションです。
- Enterprise Edition - High Performance - 高性能向けのエディションです。
- Enterprise Edition - Extreme Performance - 最高性能が必要な方向けエディションです。
- Enterprise Edition - Developer - 開発者向けのエディションです。
-
シェイプ
 - 任意に選択できます。(集合ハンズオン環境の場合は VM.Standard2.1 を指定してください)選択したシェイプによりメモリやネットワーク帯域幅が自動決定されます。
- 任意に選択できます。(集合ハンズオン環境の場合は VM.Standard2.1 を指定してください)選択したシェイプによりメモリやネットワーク帯域幅が自動決定されます。シェイプの選択時には、利用している環境のサービス・リミットにご注意ください。初期状態でリミットが 0 の場合、作成できないシェイプもあります。サービス・リミットについては OCI コンソールにアクセスして基本を理解する - Oracle Cloud Infrastructure を使ってみよう (その 1) の内容もご確認ください。
Real Application Clusters (RAC) 環境を構築する場合は、Enterprise Edition - Extreme Performance、適切なシェイプ、Grid Infrastructure が必要です。BaseDB では 2 ノード構成の RAC 環境を構築できます。
その他シェイプの情報はOracle Base Database Service 技術詳細も参照ください。

-
ストレージ管理ソフトウェア - 下記いずれかから選択します。
- 論理ボリューム・マネージャ - Linux 標準のボリューム管理です。高速な Single 構成に最適です。
- Oracle Grid Infrastructure - Oracle のストレージ管理ソリューションです。一部エディションでは 2 ノード RAC 構成も可能です。
-
ストレージのパフォーマンス
 - 下記のいずれかを選択します。
- 下記のいずれかを選択します。- より高いパフォーマンス - 大規模データベースなど、可能な限り高いパフォーマンスが必要な IO 負荷の高いワークロード向けです。
- バランス - ブートディスクや多くの標準的なワークロード向けで、ランダム I/O を含みます。
-
使用可能なデータ・ストレージ
 - データ・ストレージ容量を選択します。今回はデフォルト値の256を指定してください(プロビジョニング後の変更はできません)。
- データ・ストレージ容量を選択します。今回はデフォルト値の256を指定してください(プロビジョニング後の変更はできません)。 -
DB システム構成
 - 1 または 2 を選択してノード数を指定します(プロビジョニング後の変更不可)。
- 1 または 2 を選択してノード数を指定します(プロビジョニング後の変更不可)。- Single 構成は1を、2 ノード RAC 構成は2を選択してください。
Real Application Clusters (RAC) 環境の構築には、Enterprise Edition - Extreme Performance、適切なシェイプ、Grid Infrastructure が必要です。BaseDB では 2 ノード構成の RAC も可能です。

-
SSH キー - SSH 接続用の公開鍵・秘密鍵を登録または作成します。
- SSH キー・ペアの生成 - 新規に生成する方法です。
- SSH キー・ファイルのアップロード - お手持ちの公開鍵ファイルをアップロードできます。
- SSH キーの貼付け - クリップボードから直接貼り付けできます。
-
ライセンス・タイプ
 - 下記いずれかを選択します。
- 下記いずれかを選択します。- ライセンス込み - 新規の Oracle Database ソフトウェア・ライセンスとデータベースサービスをサブスクライブします。
- ライセンス持込み(BYOL) - 手持ちの Oracle Database ソフトウェア・ライセンスを利用できます。
-
仮想クラウド・ネットワーク - 第 2 章で作成した仮想クラウド・ネットワークを選択します(プロビジョニング後に変更不可)。
-
クライアントのサブネット - 任意のサブネットを選択します(本ハンズオンではパブリックサブネットを選択してください。プロビジョニング後の変更不可)。

- ネットワーク・セキュリティ・グループを使用してトラフィックを制御 - 1 つ以上のネットワーク・セキュリティ・グループ(NSG)に BaseDB を追加する際に利用します。今回はデフォルトのままオフにしてください。
- ホスト名接頭辞 - ホスト・ドメイン名の接頭辞として使う任意の文字列です(プロビジョニング後の変更不可)。
- ホストおよびドメイン URL - ホスト名接頭辞およびホスト・ドメイン名から自動表示されます。
- IPv4 アドレス割当て - 下記から選択できます。
- サブネットから IPv4 アドレスを自動的に割り当てます - サブネットから自動割当てされます。
- IPv4 アドレスの手動割当て - 手動で指定できます。
- 診断収集 - 以下のいずれかを有効化できます。ユーザーと Oracle Cloud Operations は、これにより問題の特定や解決が迅速になります。
- 診断イベントの有効化
- ヘルス・モニターを有効にする
- インシデント・ログとトレース収集の有効化

- 拡張オプションの表示 - 拡張オプションを表示することで、以下が設定できます。
- 管理 - フォルト・ドメインやタイムゾーンの指定ができます。
- セキュリティ - セキュリティ属性の追加や ZPR ポリシーでリソースへのアクセスを制御できます。
- タグ - フリーフォーム・タグや定義済タグでリソースを整理できます。

- データベース名 - 任意のデータベース名を指定します(変更不可)。
- 一意のデータベース名の接尾辞 - DB_UNIQUE_NAME の接頭辞となる任意の名前を指定します(変更不可)。
- 統合監査 - 統合監査を有効化するか選べます。すべてのコンポーネントの監査証跡が統合されます。今回は無効のままです。
- データベースのバージョン - Oracle Database のバージョンを今回 19c としてください。利用可能なバージョンはシェイプによって異なります。
- PDB 名 - プラガブル・データベースの名前を指定します(変更不可)。
- パスワード - 任意のパスワードを設定します(sys スキーマ用。例: WelCome123#123# ※必ずメモしてください)。
- 管理者パスワードを TDE ウォレットに使用 - 今回はデフォルト(有効)のままにします。

- 自動バックアップの有効化
 - Oracle Database の自動バックアップサービスです。今回はオフのままとします(任意で有効化可能)。
- Oracle Database の自動バックアップサービスです。今回はオフのままとします(任意で有効化可能)。
詳しい手順は 107: Autonomous Recovery Service (RCV/ZRCV) をセットアップしよう をご確認ください。

- 拡張オプションの表示 - 押下すると下記の設定ができます(文字コードを選択できることを確認してください)。
- 管理 - 文字セットや多国語文字セットを指定できます。
- 暗号化 - キー管理方法(Oracle 管理キー/顧客管理キー)を選択できます。
- タグ - フリーフォーム・タグや定義済タグでリソースを整理できます。

すべての入力が完了したら、作成をクリックします。DB システムの作成がバックグラウンドで開始され、「プロビジョニング中」から「使用可能」に変われば準備完了です。

-
作成した DB システムへ SSH でアクセスします。
-
DB システム詳細画面の「ノード」タブで、パブリック IP アドレスをメモします。

-
任意のターミナルソフトを起動し、以下の情報で ssh 接続します。
- IP アドレス - 上で確認したパブリック IP アドレス
- ポート - 22 (デフォルト)
- ユーザー - opc(DB システム作成時に準備されています)
- SSH 鍵 - 作成時に使用した秘密鍵(集合ハンズオンの場合は講師の案内する鍵を使用)
- パスフレーズ - 秘密鍵にパスフレーズが設定されていれば入力してください(集合ハンズオンでは未設定です)
接続が成功すると、下記のように opc ユーザーでインスタンスにログインできます。
$ ssh opc@<IPアドレス> -i <秘密鍵ファイルのパス> Last login: Tue Sep 16 06:39:47 2025 from 58.157.55.63 [opc@BaseDB ~]$
opc ユーザーは sudo で root 権限を取得可能です。 また、入力した情報にもとづき Oracle Database の作成・起動状況を確認できます。
[opc@BaseDB ~]$ sudo su -
Last login: Tue Sep 16 04:17:56 UTC 2025
Last failed login: Tue Sep 16 06:42:55 UTC 2025 from 193.46.255.244 on ssh:notty
There were 724 failed login attempts since the last successful login.
[root@BaseDB ~]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
[root@BaseDB ~]# ps -ef | grep mon_
oracle 20648 1 0 03:32 ? 00:00:00 ora_pmon_DB0815
oracle 20712 1 0 03:32 ? 00:00:00 ora_smon_DB0815
oracle 20732 1 0 03:32 ? 00:00:00 ora_dmon_DB0815
oracle 20738 1 0 03:32 ? 00:00:00 ora_mmon_DB0815
oracle 20746 1 0 03:32 ? 00:00:00 ora_tmon_DB0815
root 45945 45684 0 06:44 pts/0 00:00:00 grep --color=auto mon_
[root@BaseDB ~]#
DB システムには管理用コマンド dbcli が用意されています。 root ユーザーの PATH には dbcli の場所が登録されています。 下記コマンドで DB システム情報を確認します。
[root@BaseDB ~]# dbcli describe-system
DbSystem Information
----------------------------------------------------------------
ID: 5377e621-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Platform: Vmdb
Data Disk Count: 0
CPU Core Count: 4
Created: August 15, 2025 at 6:11:46 AM UTC
System Information
----------------------------------------------------------------
Name:
Domain Name: sub10xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.com
Time Zone: UTC
DB Edition:
DNS Servers:
NTP Servers: 169.xxx.xxx.xxx
Disk Group Information
----------------------------------------------------------------
DG Name Redundancy Percentage
------------------------- ------------------------- ------------
[root@primary ~]#
また、以下のコマンドで、データベースの一覧を閲覧します。
[root@BaseDB ~]# dbcli list-databases
ID DB Name DB Type DB Version CDB Class Shape Storage Status DbHomeID
---------------------------------------- ---------- -------- -------------------- ---------- -------- -------- ---------- ------------ ----------------------------------------
6a31exxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DB0815 Si 19.28.0.0.0 true Oltp LVM Configured 448f0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[root@BaseDB ~]#
dbcli のその他のコマンドの詳細については、dbcli –help または Oracle Database CLI Reference をご確認ください。
作成したデータベースにログインしてみましょう。
上記で作成した DB システムでは、1 つのコンテナ・データベース(CDB)上に、デフォルトで 1 つプラガブル・データベース(PDB)が作成されます。
ここでは、PDB 上にスキーマを一つ作成しましょう。
上記手順にて、BaseDB の OS に root ユーザーでログインしていることを前提にします。
- root ユーザーから oracle ユーザにスイッチします。
[root@BaseDB ~]# su - oracle
Last login: Tue Sep 16 06:49:41 UTC 2025
[oracle@BaseDB ~]$
- sys ユーザーで CDB にログインします。
[oracle@BaseDB ~]$ sqlplus / as sysdba
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Sep 16 06:50:48 2025
Version 19.28.0.0.0
Copyright (c) 1982, 2025, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 19c EE High Perf Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.28.0.0.0
SQL>
- デフォルトで作成されている PDB を確認後、PDB インスタンスに接続します。(例:PDB1)
SQL> show pdbs
CON_ID CON_NAME OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
2 PDB$SEED READ ONLY NO
3 PDB1 READ WRITE NO
SQL> alter session set container = PDB1;
Session altered.
SQL>
- PDB 上にスキーマを作成します。
尚、ここでは便宜上、最低限必要な権限を付与していますが、要件に応じて権限・ロールを付与するようにしてください。
SQL> create user TESTUSER identified by WelCome123#123# ;
User created.
SQL> grant CREATE SESSION,CONNECT,RESOURCE,UNLIMITED TABLESPACE to TESTUSER ;
Grant succeeded.
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 19c EE Extreme Perf Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.28.0.0.0
[oracle@BaseDB ~]$
次に作成したスキーマにアクセスしてみましょう。
一般的には tnsnames.ora にエントリを追加してログインされることが多いかと思いますが、ここでは便宜上、簡易接続方式を利用し、作成した PDB 上のスキーマに直接アクセスしてみます。
- OS ユーザを grid に変更し、接続情報(ポート番号、サービス名)を確認します。
以下では、例として lsnrctl を利用していますが、他の方法で確認いただいても OK です。
lsnrctl status

- 上記で確認した値を利用して接続します。
SQL*Plus を利用する場合は、以下のようにホスト名、ポート番号、サービス名を指定します。
($ sqlplus <スキーマ名>/<パスワード>@<ホスト名>:<ポート>/<サービス名>) <ホスト名>:<ポート>/<サービス名>は DB システムの詳細画面 → データベースの詳細画面 →PDB の詳細画面 →PDB 接続を開き簡易接続からコピーできます。
[oracle@BaseDB ~]$ sqlplus testuser/WelCome123#123#@xxx.xxxxxxxx.xxxxivcn.oraclevcn.com:1521/PDB1.xxxxxx1xxxxx20.xxxxvcn.oraclevcn.com
SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Sep 16 07:07:02 2025
Version 19.28.0.0.0
Copyright (c) 1982, 2025, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 19c EE Extreme Perf Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.28.0.0.0
SQL> show user
USER is "TESTUSER"
SQL>
以上で、この章の作業は完了です。